私の憂鬱。
第十一話
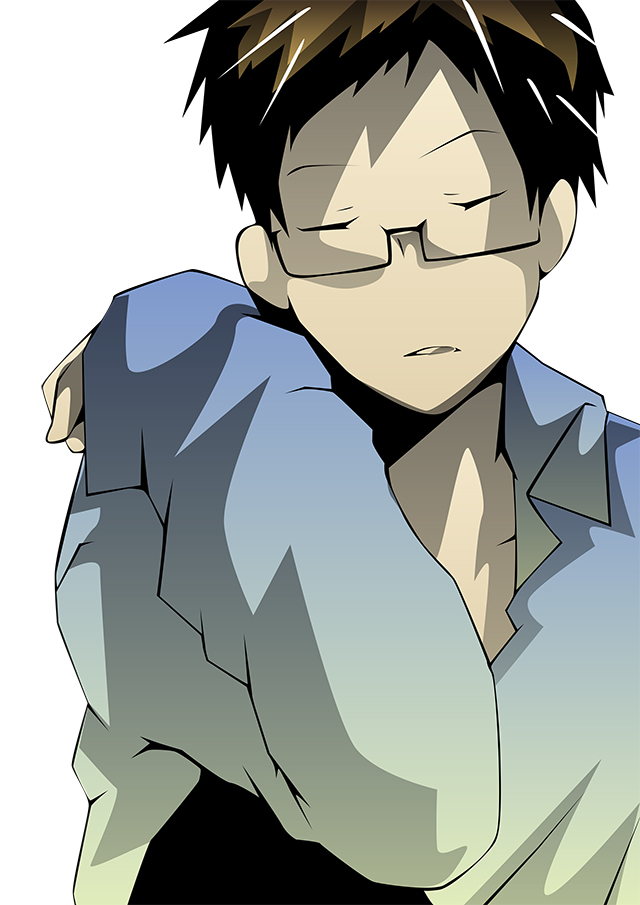
「深咲さーん、中道さん三時頃うかがいますって」
「あらそう。じゃあ新、悪いけどお茶の用意お願いね」
「了解ー。あ、なんかもうひとり編集のひとが来るって言ってたよ」
「ああ…そういえば担当が今度からかわるって言ってたからその顔見せね」
「担当さんって男が多いの?」
「そんな事ないわよ」
「ふぅん…」
新からなんとも面白くない、と言いたげな目を向けられる。
まあ…確かに作家の出会いってそのくらいしかないけれど。打ち合わせと称して頻繁に会ったりできるしねえ。
個人的に私は対象外っていうのが結論だ。
例えば気持ちを伝えて駄目だった場合かなり気まずいし、うまくいったらいったで揉め事があった場合にやっぱり気まずい。
仕事に私情を持ち込むなとは言っても、担当とデキてしまった場合、色々ときついものがあると思う。
万が一好意を抱いてしまったとして…理想的なのは配置換えになったときに想いを伝える、とか。まあ、ひとによるけれど。佐倉には発破かけるようなこといっつも言ってるわけだし。
他人事だからね、結局。
あ、佐倉もそれを待ってるからなにもしないのか、今は。
なんとなく思考回路が似ている気がして心外だ。
「…あと二時間か。じゃあ私はそれまで書斎にいるから来たらすぐに呼んでもらえる?」
「うん、お仕事頑張ってね」
にっこりと微笑まれたので、私もうなずいて書斎へとむかう。
うーん、やっぱり楽ね、色々と。
玄関の呼び鈴が鳴った事に全然気が付かなくて、耳に息を吹きかけられたことで覚醒した私は思わず悲鳴をあげてしまった。
随分と集中していたらしく、耳元で囁く新にまったくもって気付かなかったのだ。
「ちょ、驚かせないでよ!」
「だって深咲さん呼んでも気付かないんだもん」
「だからって耳に息を吹きかけることないでしょ!」
「え、ひょっとして弱いの?」
「馬鹿!客を待たせてるんでしょう、すぐ行くわ」
「うん」
先に行ってるね、と新が書斎をあとにする。
私は息を吐いて眼鏡を外し髪をほどけばコキコキと首を回した。
よし、いこう。
茶の間へと向かうと、座布団に座っていた中道がにっこりと笑って立ち上がった。
「成島さん、お久しぶりです!今回もきちんと〆切を守っていただいて。いつもありがとうございます」
「いえいえ、私の取り柄といったらそれくらいですから」
「またまた!謙遜はあんまりなされると嫌味にもとれちゃいますよ」
「中道さんこそ。ほめたってなんにも出ませんよ。あ、美味しいお茶くらいはだしますけど。こちらの進藤が」
私が冗談めかしてそう言えば、中道が破顔する。
すっかり新を気に入ったようだ。
電話応対も随分としっかりやってくれていたみたいだしね。
新って社会人経験あるんじゃないのかしら。
「有能な秘書が付いたような感じですね。これならまたちょっと無茶なお願いしても大丈夫そうかなあ?」
「結局それですか」
「あはは、こっちも人気作家さんの原稿はやっぱり欲しいですからね。…あ、そうだ、忘れてました。今度から担当が変わりますので、顔見せも兼ねて一緒に…冴島です」
「え…」
立ち上がってこちらに中道が駆け寄って来てくれていたから今まで視界に入らなかった。
ゆっくりと立ち上がって中道の傍らに立つその男に私はついつい驚愕の瞳をむけてしまった。
冴島、という苗字にもびくり、としたけれど、まさか…。
「冴島一哉です。よろしくお願いします」
お辞儀をされたあとに渡された名刺の名前を、凝視する。
ああ、本当だ。間違いない。じゃあ、その顔も?
ゆっくりとその顔を確認すれば案の定。
…一哉。
「成島さん?」
訝しんで私をうかがう中道の顔に我に返れば私ははっとして声をあげた。
「ああ、ごめんなさい。昔の知り合いに似ていて驚いたんです」
「…私がですか?」
冴島の顔を見て、今度はきっちりと微笑む。
ガラにもなく動揺するなんて、どうかしてるわ。
「名刺、頂戴しますね。こちらこそ、よろしくお願いします」
私もお返しにと名刺を渡す。冴島がそれを受け取った。
「本当にごめんなさいね。知り合いっていうのが、もう亡くなっている方だったものだから。幽霊だと思ってしまったわ」
苦笑して私が答えると、中道はリアクションに困って狼狽する。
一方の冴島はといえば…あはは、いやね。顔が引き攣ってるわよ。
「おふたりとも、お気になさらないで。もう随分と昔の話なのよ。思い出話だって平気で出来るくらい」
「あ、ああ、そうですか…すみません。こういうときってお恥ずかしながらどう反応すればいいのか戸惑ってしまって」
「ええ、私もそうですから。本当に変な事を言ってしまって。それじゃあ、打ち合わせを始めましょうか?」
「そうですね。…おい、冴島?」
「あ、ああ、すみません。そうですね、始めましょう」
ぼんやりしていた様子の冴島は、中道にしっかりしろよ、と、つっこまれつつも座に着いた。
…これからは、彼が私の担当になるということか。
まったく、まいったわね。
まあ…向こうがどう思っているかなんてわからないけれど。
「はい、それじゃあ、またよろしくお願いします。もう一回こちらにうかがったら、僕と成島さんの仕事は最後ですね」
「…なんか、寂しくなりますね」
「またいつでも連絡してくださいよ。こいつが使えなかったら僕に抗議の電話バンバンください」
「ちょ、先輩!」
「あははは、そのときはよろしくお願いします」
「成島さんまで!実際に仕事する前からやめてくださいよもう」
こうして冗談を言い合って笑えている。
ということは、むこうだってなんの感情も抱いてないはずだ。
よかった、うん、大丈夫だ。面倒な事は御免だものね。
「それでは、これからよろしくお願い致します」
「こちらこそ。お世話になります」
お互いに挨拶をして、玄関先で新と見送って別れた。
去っていく足音に安堵の息を漏らすと、顔がゆるんでくのがわかる。
あーほんと、つっかれた!
「新ぁ、お茶ちょうだーい。熱めが良い」
「はいはい」
くす、と笑って新がぱたぱたと台所へ向かう。
…なんかすっかり甘えちゃってるわね私。こき使ってるとも言うか。
私も新に続いて茶の間の座布団にどか、と座る。
「はー、これでとりあえず言われた所を直せば今回は終了ね」
「お疲れ様、あとちょっとだね」
ことん、と湯呑みを置いて新たがにっこりと微笑む。
うーん癒し系男子め。
「ありがと。新も今日はお疲れ様」
こくり、と一口飲めば口いっぱいに広がる程よい渋味。
うーん日本人で良かった。美味しい。
ふやけきった顔をしていると、じっと新が私を見ているのに気付く。
頬杖を付いてのぞきこむその視線に恥ずかしくなって、私は少しだけ眉間に皺を寄せた。
「…な、なに?」
「深咲さんのぉ、そんな顔を見れる男って僕だけ?」
「はい?」
「ほにゃ、ってしたゆるーい笑顔。僕その顔すっごい好き。かぁわいいんだもん」
そういう自分こそ思いっきり緩みきった笑顔ですけど、新さん。
しかしなんだってこう平気でそんな事を言うかな、この子は。
あまりにも恥ずかしくて居た堪れない。
「…こんな間抜け面が好きだなんてマニアックな子ねえ」
「えー?なんで?深咲さん鏡でその顔見たことないでしょ。あ、今度写真撮ってあげる!そしたらわかるよ、ほんとに可愛いの!」
「嫌よ、こんなときの顔を形に残すのは!」
「…まあ、確かに記録に残ったら誰でもみれちゃうね。僕も嫌だからやっぱりやめておこう」
「………ああそう」
にこにこと笑う新がなんともこそばゆい。
なんだってこの子はこうも甘ったるい事ばっかり言うのかしら。
本当に年上キラーね、新ってば。
本気でホストとかむいてると思うんだけどなあ。
「…冴島さんってさあ」
突然新の口から飛び出したその単語にびっくりして
思わず私は小さく揺れてしまった。
…まずい、そんなに大きいリアクションではなかったけれど
新はそう鈍い子ではないのだ。
その証拠に、新が先程の満面の笑みをどこへやったのか
私の事を半ば睨むかのような表情で目を細めみつめている。
「やっぱり元彼なんだ」
「やっぱりってなによ、やっぱりって」
「わかんないわけないじゃん、さっきも今もこんなリアクションしておいて」
……ですよね。
…まいったなあ、中道さんには察してほしくはないけど。
もし気付いても胸の中にそっとしまっておいてくれないかしら。
「まあ、むこうもなんにも思ってないでしょう。こんな偶然があるなんてねえ、皮肉なもんだわ」
「そんなのわからないよ。深咲さんにまだ未練があるかもよ?」
「まさか。もう随分昔の話よ。ありえないわ」
「甘い。ありえないなんてことはこの世にありえない!」
新の言葉遊びに私は眉を顰める。
…そういう日本語をあんまり操るんじゃありません。
「わけのわからない事を言うんじゃないわよ」
「昔って、何年付き合ってて、何歳の時に別れたの?」
「えー…一年付き合って、別れたのは20歳の時だから…もう七年前の話ね。ななねん…は、はたちでななねん…!!」
ああ、言ってて落ち込んできた。若さって眩しい。
というかなんだって素直に昔の男の話を私は語っちゃってるのかしら。
「一年て、そう短くもないじゃないか」
「そうかもしれないけど。長くもないでしょ」
「…19歳の時に付き合い始めたんだ。ひょっとして深咲さんの処女奪ったのって冴島だったり?」
「…………」
なんでそういう事を思い出させるかなあ。
初めての男っつったって。
別に私は特別な執着を持ったわけでもないし、かといってものすごく嫌な思い出があるわけでもない。
正直な話、彼の存在なんて無に近いのだ、今の私の中で。
しかし新は何を思ったのかものすごーく不機嫌な顔をしている。
「ちょっと、新」
「今すっげえしたいんだけど」
「はい?」
「僕ので上書きしたい」
「新、あのね?特別な思い入れもないわよ私。動揺はしちゃったけど、それは本当に純粋にびっくりで、私の中では忘れられた人間だったもの」
「でも、深咲さん、なんか必要以上に冷たい態度だった気がしたけど?」
「ああー…ちょっとね、思い出したのよ顔を見た瞬間。最後の最後はあんまり良いものじゃなかったからね」
「…訊いたらまずい?」
「いいけど。…なんか楽しい?」
「楽しかないけどさ。今後の対策としてっていうか」
新の言葉に私は呆れ気味にため息を吐きつつも、隠す必要もないっていうのが結論だったので、
少し苦いものを感じつつ別れの瞬間を思い出していた。
「俺にとって、深咲はもう居てもいなくても良いような存在になってしまったんだ。この先付き合った所でなにもプラスになるとは思えない。
深咲だって、似たような気持ちなんだろう?お前はおおよそ何事にも執着しないタイプの人間だから。お互いに惰性で関係を続けても仕方がない、別れよう」
「………」
「って言われたもんだからね、私はそうね、って言ってあいつと別れたわけなのよ。……新?」
目の前で固まる新は無反応だ。
なにを考えているのかわからなくてちょっと怖い。どうしたのだろう。
「…ふざけんなよ」
「へ」
「深咲さんと一緒にいて、幸せを感じるどころか、居ても居なくてもいいってなんだよそれ!頭おかしいよそいつ!!」
「いや、でもほら、一年経っての結果なわけよ。新とはまだ出会って、あともうすぐで一ヶ月じゃない。今はそう感じてくれてるかもしれないけど、先はわかんないわよ」
「僕は、深咲さんがの傍に居られる事でしか生きてるって感じないんだよ。気持ちが変わるなんてありえない」
「新、ちょっと重たいわ」
「深咲さんのサドー!」
新の言葉に苦笑しながら答えれば、新が半泣き状態で叫ぶ。
そうは言っても。表現としてそれはどうなのかしら。
「まあ、そんな別れ方をしているわけだから。きっと大丈夫よ。何も起きやしないわ。いつまでもそうやって拗ねるのはやめなさい」
その言葉にむっとしたのか、新は私の傍らへと寄れば、ぎゅ、と私を抱きしめた。
なんとなくそうだろうな、とは思っていたけれど案の定。
そのまま私にキスを落とす。
ちゅ、という音と共に新の口が私の唇を吸い上げる。
その感覚に痺れを覚えて私は小さく声をあげてしまった。
…なんというか、気持ち良いとか思わなければもっと拒否も出来るんだろうけど。
淡白なはずなのに、新の施すそれらはすごく気持ちが良い。
いやらしい意味合いではなく純粋にふわふわとした心地になる。
…まあ、続けていればそういう艶っぽい事も思うけど。
「ん、新…もういいでしょ」
「……深咲さん、約束、破ったりしないよね?」
「だから、むこうがそんな気ないってば」
「……………うん」
―――――――――――――――――――――――――――――――
「…はい、それじゃあこれでいきましょう。今回のお仕事は、これですべて終了です。お疲れ様でした」
「お疲れ様です。中道さん、今までありがとうございました。またそのうち、ご一緒にお仕事できる機会があればいいなと思ってます」
「ええ、僕もですよ。成島さんとの仕事は本当に楽しかったですから。これからは冴島にバトンタッチしますんで、よろしくお願いしますね」
「はい。うまくやっていけたら良いんですけれど」
「基本的に人当たりのいい奴なんで大丈夫だと思いますよ」
「そうですか、それを聞いて安心しました」
にこやかに微笑む顔とは裏腹に私は心の中で呟く。
愛想ふりまくのがうまいだけでしょう、と。
まあ、あの男はおおよそ好青年と言っても良かった。
別段遊ばれたとも思っていないし、付き合っている間は大事にされていたのだろうと思う。
彼と付き合ったきっかけは佐倉だった。
大学が違う私と冴島との出会いは大学の文化祭。
友達だと言って彼を連れてきた佐倉が案内をしようとしていたのだが、当時付き合っていた彼女と揉め事を起こしそれにかかりっきりになってしまった。
そこで私が案内役を頼まれてしまったのである。
元々そこまで人見知りでもないし、佐倉と趣味が同じだということもあって話題には困らなかった。
すっかり意気投合した私達は、連絡先を交換し何回かふたりで会ったあと程なくして交際を始めたのである。
結局、自然消滅に近かったのかもしれない。
頻繁に会いたがる彼に私はどこか疲れていて段々とその頻度は減っていった。
私は元々、遠出をしたりだとか精力的に遊ぶという行為が、さほど好きではなくて、でも彼は新しい場所を開拓するのが好きだった。
人混みが苦手ということもありお互いに段々とズレが生じてきたのだ。
ロマンチックな言い方をしてしまえば私はいっしょにいられるだけで良かった。
家が近かったからそこまで会う頻度は少なくなかったし、たとえば週末に遠出をするとか、そんなもので良かったのだ。
お互いに講義が少ない日などや平日にまで連れ出されてしまうと、どうしたって私は疲れてしまった。
土日は必ず泊まっていけと言うし、ひとりで本を読む時間がほしくて、そのうち理由をつけては帰ったりするようになっていた。
日課のように同じ場所へ出かけるのが私は好きで、お気に入りの喫茶店や雑貨屋さん。
そういうところで週末を過ごすのが好きだったのだが、趣味が合うといってもその楽しみ方が違ってしまえば、なかなか難しいものだと痛感したものである。
…映画館巡りとか彼は好きだったんだよなあ。
落ち着く場所が好きっていうのも私としては同感だけれど、それをみつけるために遠出してまで歩き回るっていうのが駄目だったんだ。
家具とか電化製品とか、ながめるのも彼は好きだったけど私だって嫌いじゃない。
けどそれもやっぱり都心の大きい所まで行ったりして、歩き回るのはやっぱり疲れてしまう。
一日に回る絶対量が多いのよね、もうとにかく。
…映画が好き、本が好き。
それは確かに共通項としてあったはずなのに。
ふたりで話をするときは本当に楽しかったのになあ。
『…なんかしみじみ追想してどうすんのかしら。』
まあ、だからこそ。
最後の言葉は衝撃といえばそうだったかもしれないな。
冷めた瞳でなんの感情もない顔で私をじっと見据えて。
別れを告げられて一週間程してから、新しい女の子と付き合い始めたと佐倉から聞いたときは
二重にちょっと驚いたもんだけれど。
…ていうか、あいつ傷口に塩を塗りたくるような真似するなよな。
二股されてたのかもしれない。
でもそれだってある意味仕方がないと思う。
…彼の言った事はすべて図星だったのだから。
『やっぱり私は、どうしようもない女だわ』
自嘲して最後に辿り着いた結論は、なんともいえないものであった。
―――――――――――――――――――――――――――
「深咲さん、それじゃあ僕ちょっと出かけてくるね。ごはんは冷蔵庫だから、ちゃんと」
「温めて食べるわよ、いってらっしゃい!気をつけてね」
後半の言葉を遮って私が続きを受け取った。
それに新がくす、と笑えば頬に軽く唇を一瞬付ける。
…なんだか外国でするようなキスだなあ。
「いってきます」
微笑んで出かける新がなんとなくいつも心配で、この前の話を思い出した。
やりたくなければやらなければいい。
けれどもきっと、やらなければと思うなにかがあるのだろう。
……でも、デートみたいな感じかと思うんだけどなあ。
前に一回だけ帰ってきた新に気付いたことがある。
本人はシャワーを浴びていたけれど、通り道に花のような香りがふわり、と漂ったから。
たぶん、香水の移り香だろうと見当をつけたのだけれど。
…でもデートならどうして帰って来ると、私のところにもぐりこんで来るのかしら。
相手のひとと、なにか割り切った関係を築いてるとか。
新は好きだけど、まったく相手にされていないとか。
……自分の目的のために利用しているからうしろめたいとか?
いつもはもう少し遅いのに今日はまだ夕方の5時。
相手に会いたいとか言われたからだったりして?
……まあ結局、想像は想像でしかないのよね。
お茶でも飲もうと台所に向かったそのときだ。
玄関のチャイムが鳴り響いた。
…誰かしら?
新が居ないから自分で出なくては。
私は、はーいと声をあげてパタパタと玄関扉へ向かう。
からり、と扉を開いたそのとき。
目の前に立っているのは、かつて付き合っていた男、今は私の担当編集者、冴島一哉であった。
なぜ?と思いながら私と彼はしばしみつめあっていた。