あとりえ透明2
「ブラックコーヒーとカフェオレ」
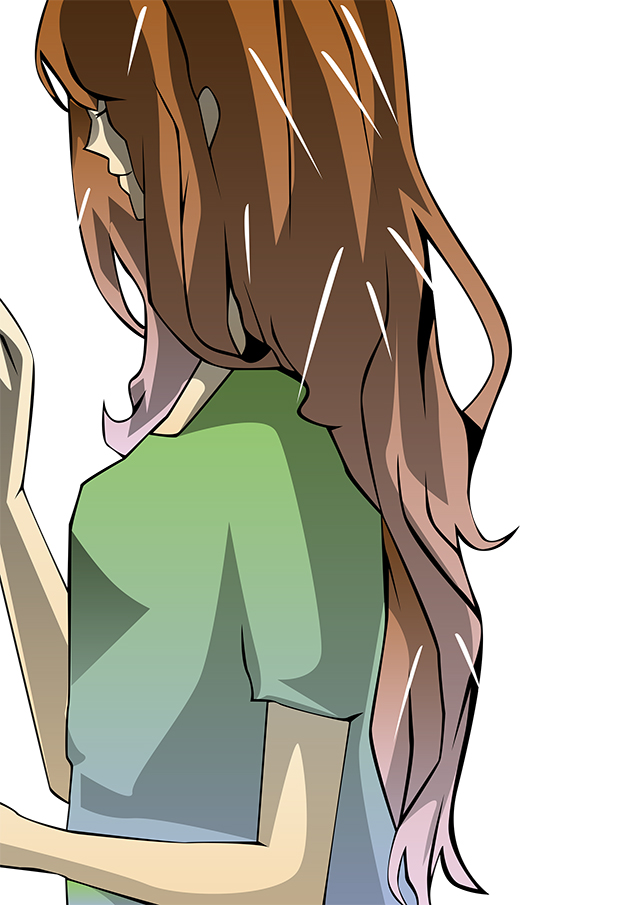
「中条せつな……侑那せつな」
朝、朝食を用意しながらポツリと呟いた娘の言葉に俺は歯ブラシを床に落とした。
「もしくは、進藤せつな。うん、こっちの方が語呂がいいな」
落ち着け。
そうだ、これは夢だ。
悪い夢だ。
もう一度眠れば目が覚める。
「って、何やってんの?お父さん」
寝室に向かおうとした俺をせつなが呼び止める。
せつなが手にしたフライパンから香ばしいシナモンの香りがする。これは間違いなく機嫌のいい時の娘特製フレンチトーストの香りだ。
いや、香りつきの夢だ。朝のアールグレイの香りも夢なのだ。
「今日、お仕事あるでしょ。私もバイトあるから早く食べちゃって」
がしりと背中を掴まれた。この感触は夢ではない。
「どこからそれを……?」
「今日10時から編集会議だってスケジュールに書いてたじゃない」
「いや、そっちじゃなくて」
娘はふふふ、と含みのある笑いを浮かべた。
「ごめんね、お母さんに会っちゃった」
あとりえ透明でアルバイトをさせた時から覚悟はしていた。
恐れていた時が来てしまったのだ。
思えば昨日はずいぶん帰りが遅かった。
自分も夜型の仕事をしているのでさほど気にはならなかったが、その時に聞くべきだったのだろう。
ざっくりとした事の顛末をせつなから聞く。ほぼ予想通りだった。絵美の相方が復帰していたのを知らなかったのは迂闊だった。
あとりえ透明のアルバイトを許可したのは「自分の知っている店だったから」という簡単な理由だった。ファーストフードや工場のルーチンワークが個人的に好きでないということもあるが。
あの店にもう侑那絵美も松島朋もいないということで油断はしていた。
「朋さんに連れて行ってもらったのっ。元気だったよっ。お母さんすごい美人でっ!」
「あ……ああ……」
「なんかねっ、おっとりさんだったっ。かわいい感じっ」
「……俺のことなにか言ってたか?」
「うんっ」
せつなは満面の笑顔で紅茶を飲んだ。
「次はお父さんも連れて来なさい、って」
俺はテーブルに頭を打ち付けた。
夢なら 早く醒めてくれ
嫌味なんだろう
あの侑那絵美が嫌味を言えるようになったとは、随分な進歩だ。
そこまで世を拗ねさせたのは間違いなく自分なのだが。
「今日ね、夕方からあとりえ透明にお母さん来るんだって。お父さんも来ない?」
「絶対行かない」
フレンチトーストを掻きこむと、通勤バッグを手にとった。
「もー、お父さんのケチー」
別に会いたいわけじゃないんだ。
ただちょっと近くに寄って、暑いから喉が渇いて、でも近くに自販機もコンビニもなかったから。
「お父さん、いらっしゃいませっ」
こちらがドアを開けるより先にあとりえ透明のドアが開かれた。
そうだ。この子は足音で誰か分かるんだ。
「もうちょっといいノイズキャンセル探そうか……」
「えー、今のでちょうどいいよっ。あんまり高いのだと失くすの怖いしっ」
「いや、俺がな……」
改めてせつなの姿に目をやる。黒いロングスカートのエプロンドレス。写真を見せてもらったことはあったが、よく似合っている。
「その声はー成瀬さんだねー」
せつなの後ろから懐かしい声がした。
不揃いに伸びた栗色の髪は束ねられゆったりとしたチュニックにスラックス。松島朋に付き添われ、白い杖をつきながらゆっくりと歩いてきた。
「お久しぶりですー。成瀬さん」
「侑那絵美……」
「進藤笑、ですよー」
ふふふ、と笑うその姿は14年経っても変わらなくて。
年を取っているはずなのに、何も変わらなくて。
卑怯だ。
やっぱりこの女はどこまでも卑怯だ。
「せつなちゃんをこんなに立派に育ててくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします」
見えないはずなのに正確に俺の前に歩み出て頭を下げる。
「お前は……文句を言わないのか?言いたいことなら山ほどあるだろう?」
「何もないよー。せつなちゃんに会えただけで満足。これ以上欲張りなこと言ったらバチが当たっちゃうよー」
「なんで……」
「なんでって?」
侑那絵美は小首を傾げて微笑む。
「分かんないなー。私ばっかり勝手言ったのに、娘がこんないい子になってて、私はそれがとにかく嬉しくて、何を不満に思えっていうの?」
ああ、彼女はどこまでも相変わらずなんだ。
世を拗ねてなんていなかった。
純粋に話したかっただけなんだ。
目が見えなくなっても
絵が描けなくなっても
世界をとにかく愛していてやまない。
「欲を言うならー、そうだなー、小さい時からの写真を順番に見たいかなー」
全てを愛してやまない。
「七五三とかー、小学校の入学式とかー、運動会とかー」
自分以外の世界をとにかく愛している。
「あーあ、目が見えたらなー」
必死に愛そうとしている。
「だからねーいろんな話を聞かせてよ」
誰も知らない場所でも それは続けられ
「趣味とか、好きな食べ物とか、得意な科目とか、あ、絵は?」
それは見ていてひどく ひどく 痛々しいほどに
「絵を描くのは……好……」
俺は侑那絵美を……いや、新藤笑を抱きしめた。
「成瀬……さん……?」
「もう、いいから……もういいから……話そう。いろいろ話そう……だからもう……」
彼女はこの14年間を、どんな思いで過ごしていたのか。
「もう……笑わなくていいから」
一人で
一人きりで
それでも
世界を憎むことは許されず
人に甘えることも知らず
俺が娘の成長に一喜一憂している時も
それを見ることも聞くことも叶わず
桜が舞う春も 入道雲の広がる夏も
紅葉の散る秋も 雪の積もる冬も
季節の色を窺うことすら許されず
ただただ思いを馳せながら
それでも 全てを愛し 微笑み続けていた。
それは 一体
どれほどの絶望なのだろうか。
「笑……」
最初からそうすればよかったんだ。
誰かではない。
他の誰でもない。
俺が救うべきだったんだ。
責めるばかりで、どうして気づいてやれなかったのか。
「一緒に暮らそう」
「成瀬……さん……」
「せつなと……三人で……暮らそう」
今までの分も、これから泣けばいいんだ。
お前は子供のように泣いて笑って、せつなの声を聞いていればいいんだ。
「うーん、困ったなー」
笑は目を潤ませて微笑む。
「それはちょっと幸せすぎて神様に怒られちゃうよー」
「怒られろ。お前はそのくらいでちょうどいい」
何故、こいつはこんな時にでもそんなことを考えるのか。
「俺はどうでもいいんだよ。お前とせつなで、今までを取り返すくらい幸せになればいいんだよ」
「うーん、私なんかがそんなことしたら、バチが当たるよー。絶対」
せつなが一歩前に出た。
「とりあえず、中でゆっくり話したら?ブラックコーヒーとカフェオレでいいんだよね」
嬉しそうに笑うその顔がまた幸せそうで
「お父さん、お母さん」
ああ、俺の幸せはこんなところにあったんだ。