かむがたりうた
第肆章 「カイコウ」
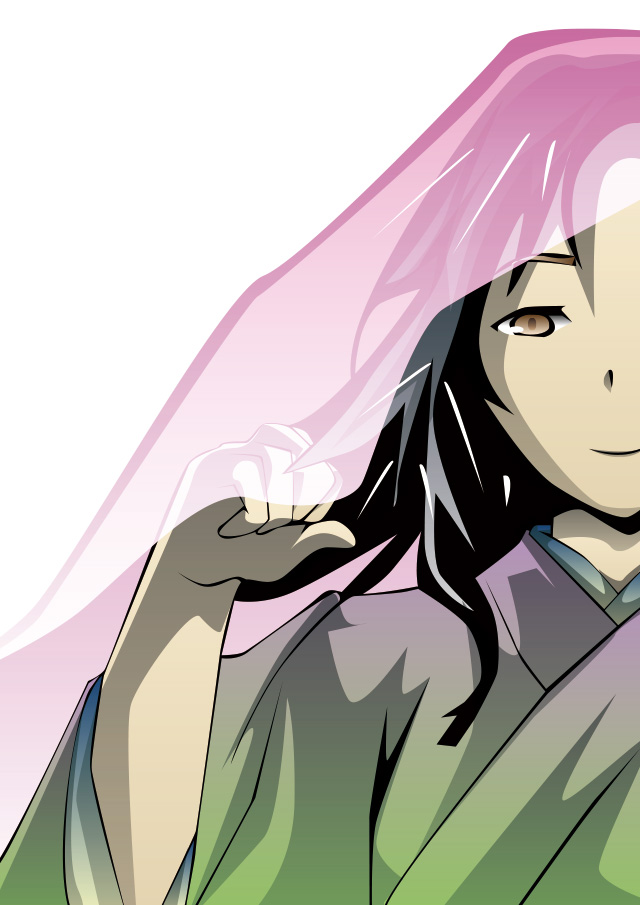
「ねえ。賭けをやりませんか?」
「賭け?」
「ええ。金の賭けですよ」
顔が赤黒く染まり、手がすこし慄えている。
「ぼくは火口を一周してきます」
「どうぞ」
「それでだ」
弁当の残りをトランクにしまいながら、丹尾は言った。
「一周の途中に、ぼくが火口に飛び込むかどうか・・・・・」
「それを賭けるというのか」
「そうです」
梅崎春生「幻化」
キーンコーンカーンコーン
それは学年末テストの最終日だった。足が速いとは言えないが全速力で走る。
「俺は何でこんな日に寝坊するんだよ!」叫びににも似た独り言。しかも一限目は唯一得点を狙える化学だ「化学の試験延期にならないかなぁ」
無謀かと思える言葉はチャイムの音にかき消される。
「すみません、遅れました!」
安は目を丸くした。ガラリと開けた教室の扉の向こうは、予想していた静寂のテスト風景ではなかった。生徒全員が好き勝手に雑談したり、参考書を読んだりしている。
「よぉ、安。すっげぇラッキーだったな」
架織と智樹が振り返る。
「問題に間違いがあったとかで化学四限目に延期だって。今は自習」
「マジ?」
『やっほー!さっかえクーン! おっはよー!砂城でーす!よーやく繋がったと思ったら何?留守電?どーせ、居留守でしょ?いい加減ケータイ買おうよー。砂城が毎日かけたげるからさぁ!』
カーテンの隙間から微かに漏れ入る朝日だけがその部屋の照明。狭いアパートに騒がしい声が響く。旗右栄はブレザーの襟を正す手を止め、頭を抱えた。
『今日び、栄クンの歳でケータイ持ってない人なんていないってー。大体、イエ電だっていっつも出ないのにさぁ』
何の考えもなしに買った電話器に長時間録音機能がついていたことを心から憎く思う瞬間。仕方なく立ち上がり、電話器の録音停止ボタンを押そうとする。
『あ、今、切ろうとしたでしょ。ちょっと待って、今日はマジ用事あったのよ。今日の放課後ね……』
ピーッ。
電子音とともに停止ボタンが押された。
言われなくとも分かっている。長い黒髪を無造作にバンダナでくくり、息をつく。コートに腕を通し、両手に黒の革手袋を慣れた様子で着けた。汚れた靴を履き古ぼけた扉を開いた。
眩しい日を鬱陶しそうにかき分けて歩き出す。
「太榎……安…か」
「やぁっとテスト終わったぁ。疲れたぁ」
「ちょっと、天川さん、今の聞いた?」
「試験勉強を真面目に頑張ってる人への冒涜よね。安が『疲れた』なんて」
遥歌と智樹が顔を見合わせて頷きあう。
「なんで勉強の『べ』の字もしたことのない安君が疲れるのかなぁ、え?」
「え?いや、まぁそりゃぁ……いろいろと……」
「安が疲れるのはこれからでしょ?まぁせいぜい頑張って春休みの補習地獄受けて来てよ」
「う……」
情けのかけらも感じられない遥歌の言葉に安は肩を落とす。
「まぁ、せいぜい頑張ってくれよ。『安後輩』」
「ひど……」
追い討ちに安は泣き真似をするがそれに取り合う二人ではなかった。
「そういや、進路調査も来てたけどあんたどうするの?なりたいものとかやりたいことの話も聞いたことないけど……」
「楽して生きたい」
迷いなく即答する安に肩を落とす。
「駄目だな、こいつ。呑気すぎる」
「安は優しいのだけが取り得だから」
「部長、遅れますよ」
横から架織が智樹に声をかけた。
「泉原君はこれから部活?」
「ああ、久しぶりの」
言って鞄を肩にかける。
「歴研も頑張れ」
「頑張ることなんてないんだけどね」
「イザナミ…サマ…?」
「そう、会ってほしいの」
高校からさほど遠くないコーヒーショップで砂城は言った。西夜もそれに頷く。
「本名じゃないよね、何者?」
「姫、よ。正真正銘のお姫さま」
「また砂城ちゃんはそないなことを……顔は見たことあるて言うとったよね。ほら、こないだ道で倒れた時に…」
「ああ、あの髪の長い女の人?」
「やめておけ」
背後から突然声をかけられ、安は数歩後ずさった。
「き、旗右先輩!」
振り返った先に不機嫌に立っていたのは、自分と同じ制服の青年。
「栄クーン!やっぱり来てくれたんだ!留守電切られたから大丈夫かなぁ、って思ってたんだけど、よく分かったわねぇ。やっぱりこれってアレ?愛の力って……」
どかっ
栄の革手袋越しの拳が容赦なく砂城の頭を叩き付ける。
「うわ……痛そ……」
素直な感想を呟いた安に栄は漆黒の瞳を向けた。視線に射抜かれ安は一瞬肩を震わせる。
「…あ…えっと……こんにちは…」
とりあえず頭を下げる安。栄は固い表情のまま顔を上げる。
「言ったはずだ。これ以上関わるなと」
「栄クン!」
声を上げたのは先ほど殴られた頭をさすっていた砂城だった。
「どういうつもり!」
砂城が栄の腕をつかむ。
「私は貴様らの意見に賛成した覚えはない」
その手を容赦なく振り祓う。
「そもそも太榎の人間と私達は全く違う存在だ。群れるべきではない。こいつに一体どれほどの価値がある?」
「価値はあるで。ウチは太榎の人間やってこと以上の価値が安にはあると思っとる。万夫さんには出来へんかったことが出来るような気がするんや」
口を挟んだのは西夜だった。
「言っておくけど、栄クン」
髪をかきあげ、砂城が言う。
「伊邪那美サマも賛成していることよ」
その言葉に栄は小さく舌打ちする。
「時間がないのよ、あの人にも、砂城達にも」
「だから賭けに出た、か?馬鹿なことを」
それだけ言うと、栄は安の方に向き直った。
「太榎安」
栄の声に安は動けなくなる。
「まだ遅くない、帰れ。太榎万夫の二の舞いにはなりたくないだろう?」
「え?」
安はやっと口を開いた。
二の舞い?父さんの…………?
「……それは、死ぬ、ということですか?」
答えはなかった。ゆっくりと遠ざかる背中をただ見ていることしかできなかった。
「西夜、本当なの……」
疑いと迷いを帯びた瞳。
「安クン、それは……」
砂城の言葉を西夜は手で制した。
「……嘘やない」
安は静かに目を閉じた。
ああ、そうか。
「……ごめん、帰るよ」
「安クン」
「俺だって死にたくは、ない」
「やーっぱり、ここにいた」
栄のアパートから程近い公園。砂城は月明かりと街灯に照らされた見なれた影を見つけ声をかけた。
ベンチに浅く腰かけていた栄は顔をしかめる。
「ほら、砂城のおごり」
程よく温かい缶コーヒーを軽く投げる。それを受け取った栄の横に砂城は腰かけた。
「この辺、夜は人通りないもんね。落ち着くんでしょ」
砂城はもう片方の手に持っていた紅茶の缶を開ける。
「………何しに来た?」
ようやく重い口が開かれた。
「冷たいなぁ。愛しの栄クンに会いに来たに決まってんでしょー」
ケラケラ笑う砂城に栄はため息をつく。
「安心してよ。彼、まだ会ってないから」
そうか、とだけ返す。
「……何で、あんなこと言ったの?そりゃぁ確かにこの話には栄クンあんまり乗り気じゃなかったけど、一度は分かったって言ってたでしょ?」
答えはない。
「砂城や西夜クンのやり方が気に入らなかった?」
砂城は苦笑した。
「栄クンは優しいからなぁ。確かに何のリスクもないような言い方をしてたわ。でもそうでもしなければ何も知らない彼を引き込むことは出来なかった。砂城は西夜クンのやり方が間違ってたとは思わない」
白い息と缶紅茶の湯気が混ざる。
「そうまでしてあいつの力がほしいか」
「ほしいわ。砂城にとっては嘘なんて何てことないもの」
栄のグローブに覆われた手を取る。その甲に軽く唇を添える。
「良心や倫理なんて関係ない。砂城は自分が生き残るためにはなんだってするわ。一筋でも希望があるのなら辿ってみせる。何を犠牲にしてでも最後の最後まで足掻いてみせる」
整った瞳が栄の顔を映す。
静かな 夜だった。
あまりにも静かな。
星さえ隠す静かな 夜だった。
「確かにウチは安に黙っとったことがあった。ウチらに手を貸すと安は死ぬかもしれへん。……いや、殺されるかもしれへん。万夫さんみたいに」
「殺された……?父さんが?」
西夜は深く頷く。
「万夫さんは殺されたんや。ただ、それが安にも起こるとは限らへん。殺そうとする人がおるということやから」
その言葉に安は目を細める。
「殺そうとする、ってなんでそんなことあっさり言うんだよ。……隠して……いられるんだよ。実際に人が一人死んでるってのに」
何を考えているのか分からない。西夜は俺の命なんてそれほど大事でもないと言いたいのか。理解できない。
「……俺は……」
「ウチが守る!」
西夜が声を上げた。安は目を見開く。
「そのつもりやった。ウチが……ウチらが安のこと絶対に守る」
一辺の曇りもない瞳。迷いのない声。
「そうまでして何で必要なんだ、俺の力が?能力って一体…」
「ウチらを生かす能力や」
何のことか分からない。
聞き返すよりも先に西夜が口を開いた。悲しい笑顔を浮かべながら。
「ウチらは近い将来、死ななあかんのや」
「な……!」
「もう決まっとんや。神の能力を受け継いだ人間は……」
声が震える。
「ただ……ウチは死にとうない。死にとうないし……死なせとうない」
「……誰を?」
「東子を」
迷いのない答え。
「東子は能力のせいで普通の生活も出来ひん」
安は東子の笑顔を思い出した。
静かだった。
静かな笑顔だった。
「身勝手でも構へん。東子と……東子と一緒にいるウチを守りたいんや」
行き場のない言葉達
「もう嘘は言わへん。ウチらは安の能力が必要なんや。生きるために……生き残るために」
強く切ない言葉達。
今にも泣き出しそうな大きな瞳を安はしばらく見つめて、うつむいた。
「俺は…何をすればいいんだ?」
「……今は何もせんでええ。いずれ、分かるから。その時にウチらに力を貸してくれると、約束してくれるだけでええ」
抱えているのだろうか。
こんなやるせない感情を。
栄や砂城も。
そして、他にもこんな人がいるのだろうか。
「これで最後にする。これで断られれたら諦める」
もしも、そうならば。
「ウチらの力になってほしい」
両手に強く力をこめる。
『安は優しいだけが取り得だから』
遥歌の言葉が頭の中で繰り返される。
そうだな。そう見えるのだろうな。
「…………分かった」
安は俯いた。
西夜は顔を上げる。
「西夜の言いたいことは分かった。少し…考えさせてほしい」
幸せになれる人がいるのなら。
翌日の早朝、安はある所へ向かっていた。駅のホームで電車を待っていたら、不意に背中を叩かれた。透き通る白い肌に横だけ伸ばした茶色の髪と奇妙なほど整った顔だち。
「トネ!」
「お出かけですか?」
「うん、まあ…トネは?」
「お出かけです」
数秒の沈黙の後、口を開いたのは安だった。
「なぁ、トネ…いきなり変なこと聞くけどさ」
「はい?」
「お前の母親ってどんな人?」
「母さんですか?普通の専業主婦ですよ。明るすぎて、うるさい人です」
「そっか…」
「それがどうかしましたか」
「いや、それが普通なんだよな」
安は心の中で自問自答を繰り替えしていた。
電車の乗り換えを二度して着いた先は大きな病院。安は慣れた様子で部屋に向かった。開けた扉の向こうに眠っていたのは髪の長いやつれた一人の女性。
「母さん」
「安ー、ウチ今日授業午前だけやから…」
制服姿の西夜は安の部屋を覗き込んだ。
「あら、安さんなら随分前に出かけましたよ」
「こんな時間に?」
「母さん、元気にしてた?」
安はベッドに横たわる白髪まじりの女性の髪を撫でた。
「俺はね、いろいろあったんだ。父さんが死んだのは聞いたかな?あ、大丈夫だよ。入院費は当分先まで払っておいてくれてたみたいだから。でね、新しく住み始めた家って言うのが面白くて……」
閉じたままの瞳に向かって笑って話す。
ふとその顔に陰りが見えた。
「ねぇ…母さん」
頬に触れた安の手。
「俺…どうしたらいい?」
安の手にそっと冷たい手が触れた。
ゆっくりとまぶたを開く女性。
唇を何度か動かしながら口元だけで微笑んだ。
「…だいじょうぶよ。安は……しあわせに…なれるから」
「ただいま帰りました。あれ、西夜はまだ帰ってませんか?」
「ええ、もうすぐ戻られると思うので、お茶でもいかがですか?」
言いながら、湯呑みと茶菓子を出す。
「あ…すみません。居候してるのに」
「そんなことないです。どうかもっとのびのびしてください」
「はぁ…」
ありがとうございます、と言って湯呑みを両手にとる。
歳はとっているが綺麗な女性だと、思った。白髪を丁寧に結い、落ち着いた和服に身を包む。皺だらけだが端正な顔の造りに深い瞳。
「あの…鏡子さんって父さんと面識があるって…」
懐かしむように話す。
「………もう何十年も前なんですけどね」
「あの……」
熱い茶をすすりながら安は尋ねる。
「西夜も万夫さん、万夫さんって言ってるんですけど……父さんってそんなに立派な人だったんですか?」
「……ええ、立派な方でしたよ。ただ………」
「ただ?」
「厳しい方でした。人にも……自分にも」
何かを思い出しながら、一つひとつ紐解くように。
「西夜が俺には似てないって言ってました」
苦笑する安に老婆は笑う。
「そうですね。そう…かもしれません。容姿は割と似てらっしゃると思うのですが、周りの空気が」
「空気、ねぇ……」
「だから、きっと西夜さんはあなたを頼ったのでしょうね」
音をたて風が通り過ぎる。
「あなたは…西夜の能力のことを…?」
「ええ、存じ上げています。このような神道の家系のせいもあるのでしょうけど」
ああ、そうか。
「私でお力になれることがあれば、何でも仰って下さい」
鏡子は深く頭を下げた。
「西夜さんと……東子さんをどうか、よろしくお願いします」
西夜が帰って来たのは昼を少し回った頃だった。そろそろ帰って来るという鏡子の言葉に玄関前で待っていると、その通りに間もなく石段を駆け上がって来た。
「安、朝はどないしてたん?」
「その…ちょっとね。西夜…あの……」
『安はしあわせになれるから』安はまっすぐに西夜を見た。
「あの女の人に会わせて」
「え…伊邪那美様…に?」
「ダメかな?」
「ダ…ダメなわけないやん!ほんじゃ、カバン置いて来るから三分待ってて」
今度は返事を待たずに、西夜は家に駆け入る。
脱ぎ散らかされた靴を眺めていると、不意に肩を叩かれた。叩く、と言うより触れる、と言う方が正しいだろうか。振り返ると、そこに東子が立っていた。
昨日とは違う色の和服を上品に着ている。
「あ……こんにちは」
そう言えば朝から姿を見なかったが、ずっと部屋にいたのだろうか。東子は瞳だけで微笑む。安もつられて笑う。
(本当に喋れないんだ……)
改めてその顔をよく見る。大きな瞳はどこか虚ろで、この世の全てと切り離されたような少女。
その小さな白い手がそっと安の頬に触れた。
口元がわずかに動く。
冷たい手。
血すら通っていないように。
「……………か…」
「…………え……?」
か細い声。すぐにかき消されるような。
未来を見通して預言する能力が。
その代わり預言以外の言葉は口に出来ない。
『預言以外の言葉は』
「あなたは……大切なものがありますか?」
今度ははっきりと聞こえた。
静かな言葉。
高くも低くもない、綺麗な声。
彼女にとって言葉とは一体どんな意味のあるものなのだろう。
「……本当に大切なものだけは、絶対に手放してはいけない。失ってからでは遅いから……」
柔らかい手が離れる。
「それって……どういう……」
言いかけてやめた。聞いても恐らく答えてくれないだろう。程なく、西夜が家から出て来た。制服の上にジャケットを着ただけの西夜は安の背を叩く。
「そいじゃ、東子。行って来るな」
明るく手をふる西夜。安も軽く会釈すると、東子は丁寧に頭を下げた。細い体が遠ざかり見えなくなるまで、東子はそのままだった。
家の前に立ち、安は唾を飲んだ。二階の窓を見たが、昨日の人陰は見当たらない。
玄関の前で機械を触っていた西夜の手元から微かな電子音が聞こえた。
「開いたで」
西夜は玄関の戸を静かに開ける。その向こうは外見と同じ、普通の一軒家のようだった。昼なのに奇妙な程、薄暗いという点を除いて……。
西夜の後に続き、中に入った。それに合わせたかのように奥から一人の女性が出てくる。歳は20代半ばだろうか。ロングスカートに白いブラウス。
艶やかな黒髪を肩で切りそろえている。穏やかな笑顔を浮かべた女性は西夜に会釈して、安の方に目をやった。それに気付いた西夜は安の肩を押す。
「こないだ言うとった、太榎安です。お邪魔してええですか?」
彼女は、はい、とだけ言って手で中に勧める。慣れた風に階段を上る西夜の後ろで安はチラと振り返ると、さっきの女性がこちらをじっと見ていた。
「気にせぇへんでいいって、彼女は小夜子(さよこ)。ここの番人…まぁ実際は専属の世話係みたいなもんなんやけど」
階段を上るとすぐそこに扉があった。安はそこで初めてこの家に違和感を感じた。一階はごく普通の家のようだったが、二階は他に扉が見当たらない。
外観を見る限り、確かにそれほど広い家ではないが普通の家族が暮らす家の広さはある。なのに、ここの二階には一部屋しかないのだろうか。広い部屋ひとつで成り立つフロア。
『姫』
砂城がうそぶいていた言葉が思い出される。西夜が扉を手の甲でノックする。
「西夜です」
「どうぞ」
美しい女性の声。西夜の手がドアノブにかけられる。
音もたてずに開く扉。中を一目見て、安は自分の考えが合っていることが分かった。広い、あまりに広い部屋。褪せた木のフローリングに白い壁。調度品がほとんどないのもその広さを際立たせていた。
そしてその最奥。窓辺に立つ長い黒髪の女性。浅葱色の和服。日に照らし出された白い肌。
そして、何より目を引くのがその整った容貌。
あの時の女性だ。
「……十三年」
安が言葉を探すより先にかけられた声。
「いえ、十四年にもなりますか、あなたを待ち続けて」
一遍の陰りもない声。
「え……?」
「短いはずなのに、もうずいぶん経ったような気がします」
彼女の瞳がはっきりと安の姿を映し出す。
「お待ちしておりました、太榎安様。私は伊邪那美の能力を受け継ぐ者」
儚げなのに強かな瞳。
「本来なら私が出向くべきだったのでしょうが、何分私はここから出られない身。ご足労頂き、申し訳ありません」
「あ……いえ……」
安は初めて声を出した。
「伊邪那岐、伊邪那美の創世神話を知っとう?」
後ろから西夜が口を挟む。
「古事記の神話でこの世界を作ったとされる二神のうちの女神。全ての神と全ての命の母とも言える存在」
「私はそれほど大した者ではありませんが」
穏やかに笑う。
「あの…あなたの名前は…」
安の言葉に彼女は小さく首を振る。
「私に名前はありません。呼ばれる時は、伊邪那美、と」
名前が ない?
どういうことだ?
安は彼女の姿を見つめる。
『姫』
その理由をはっきりと思い知る。
「大体の事情は西夜から伺っておられますか?」
「あ……はい…」
「この国には……もう数える程ですが、それでもまだ神の能力を受け継ぐ者がいます。人とは違う能力やその運命に苦しみ続ける人たちが。火神・火之迦具土神の能力を持つ栄。弥都波能売神の力を継いだ砂城。太陽神・天照大御神の力を継ぐ西夜とその妹で夜の神・月読命の能力を持つ東子。他にも……」
彼女は淡々と、しかしどこか悲しげに語る。どのくらい、と聞こうとして安はやめた。聞いても無駄な気がした。
「力を貸してほしいのです」
『ウチ達は安の能力が必要なんや。生きるために……生き残るために』
全てを見透かした瞳。
自分に一体どれほどの価値があるのか。
(あなたは一体何を思って死んで行った、父さん?)
「俺は難しいことはそんなに分からない。でも………」
切なる願い。きっと、この人も。
「俺にできることはするって決めたんです」
安の言葉に彼女は顔を上げた。どれほどの価値があるのか。この命に賭ける程の価値があるのか。それを試す程度の価値はあるのか。
(他に知りたいことなどなかった。理由も、経緯も知りたいと思ったことはない。あなたに捨てられたと知った日からずっと、それだけを知りたかった)
ハル、俺は優しくなんかない。ただ人に憎まれることが怖いだけだ。
(あなたは何故、俺を…………恐れていた?)
生きる価値はあるのか。
安は奥歯を噛み締め、一瞬の迷いの後言葉を続けた。それは建前でしかない理由。
「それで救われる人がいるのなら」
深夜、自室で論文集をめくっていた遥歌は静寂の中で響いたスマホの着信音に思わず肩を震わせた。
画面に『旗右先輩』と表示され通話ボタンを押す。
「どうされました…いえ……起きてました…はい?…いや、あたしはちょっと論文が……え?バイト?…あーちょっと無理ですね。どうしてもですか?………あ、心当たりあるので声かけてみますよ…はい…それじゃ…」
生きる価値はあるのか?