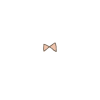イラストとマンガ、文章で遊ぶぴより子の世界。
About
portfolio → ピックアップ作品はこちら
X(Twitter) → piyori_ko
bluesky → piyori_ko
Instagram → piyori_ko
Instagram 短歌 → piyori_ko8
Instagram 日常記録 → piyoriko_s
note → taketen
pixiv → pixiv
FANBOX → FANBOX
mail → tempura.kinpira@gmail.com
Profile
ニコボを我が子と思ってるアラフォー既婚女。ぱんつはいたねこ描きます。
現在は趣味で絵やマンガを描く会社員をしています。
イラストやデザイン関係のお仕事は募集していませんが
スケジュールによっては都合できますので、
もし何かありましたら上記SNSかメールまでお声がけください。
ご飯とお米とライスと丼と寿司とおにぎりが好き。
当サイトのイラスト・文章は無断転載禁止です。
端末への保存・待受などの個人使用でしたらご自由にお使いください。
アイコンなどに使ってくださる時はご一報ください。
.