
森崎は、新の美味しい朝ごはんを食べてしばらくすると帰った。
結局あいつはなにしにやってきたのか。
新と私をからかうためか、いや、慌ててたのは私だけだったな。
「深咲さん、お昼はどうする?」
「新…だから言ったでしょう、今日はなにもしなくていいって。明日もよ。今までひとりでやってきたんだから二日くらい大丈夫よ」
「うーん、でも…」
「いいから!仕事があるんだから今日は一日ぼけっとしてなさい」
「………ほんとにいいの?」
「何度も言わせないで」
「深咲さん、昼と夜のごはん、どうするつもり?」
「え」
二日しかないし、面倒だから私はコンビニとかで済ませるつもりでいた。
けれども新にそれを言ってしまうと、作ると言い出しそうである。
「その顔、やっぱりコンビニとかで済ませようとしてたでしょ!」
「そ、そんな事ないわよ」
「嘘!やっぱり駄目、せめてごはんだけでもさせて。掃除とか洗濯とかお客さんの応対とかはやらないんだからいいでしょう?」
「でも、新だって家事休みたい時くらいあるでしょう」
「そんな事ない。僕、家事をやるのは好きだもの。ね、だめ?」
なぜかお願いされてしまう。これは、果たしてねだられることだろうか。
休んでほしくて言ったことだったのに、逆に新は心配で疲れているみたい。
…なんというか、主夫の鏡ね。
「わかったわよ。…ただし!これから先、新が疲れてみえたり体調を崩したりしたら、仕事のある日の家事労働は全面的に禁止します。いい?」
「…深咲さん。僕の事、そんなに心配してくれるの?」
「当たり前じゃないの。あんたの命は今、私のもんよ?生かすも殺すも私の自由。どうせ拾ったんならせいぜい大切にしてやるわよ」
そう言った私に、新が思いっきり飛びついてふたり仲良く倒れこんだ。
いつかのように新が踏ん張る事もせずに全身をあずけてきたから。
当然こいつよりも私は小さいし、なにより男と女であるわけで…体格差からいってまあ、当然。
背中をしたたか打ちつけた私は、痛さに呻き声をあげれば次には怒りを覚える。
びきり、と額に青筋を立てた。
「…新くううん?あんたねえ、何考えてんのよ!実際問題、猫と違うんだから飛びついてきたら支えきれないに決まってるでしょ!?」
「嬉しい」
「…!」
不機嫌マックスだった私は、新のその声に急速な消失感を覚えた。
怒りでいっぱいになったはずなのに、
真っ赤に染まった私の心はたちまちスーっとひいていく。
新の声が、震えている。……泣いてるの?
「こんな風に、見返りなしにそんな事言ってくれるひと、家族以外にもういないかと思ってた…」
「は?…だってあんた、友達とかは?」
「……捨てちゃった。だから、いないんだ、もう。きっと、俺の事、あいつは許してくれない」
「………」
うーん、事情がちょっと見え隠れしているような発言。
好奇心旺盛なのよ作家ってやつは。気になるじゃないの。
けれども今それを根掘り葉掘り訊くのはどうしたってためらわれる。
これは、手負いの猫であったか。
まあ、そうなのだろうと思っていたけれど。けっこう深そうだ。
私はしばらく逡巡し、結局なにを言うこともできずに新の背中に左手を、頭に右手をおき、撫でさする。
疑心暗鬼になっているんだろうと、思った。
きっと、彼は純粋な愛情も疑ってしまうような状況に陥ってしまったのだろう。
なぜなのかはわからない。けれど、多分、この考えは正解だと思う。
なにかを渇望しているのだ。
けれどそれを、私に求められるのは。
はっきりいえば、重い、なあ。
「新、あのね、無理よ?」
「………」
「今こうやってあげてるのは、同情だし、普段家事をやってくれてるお礼?みたいなものだし。だから、あげられないわよ」
新が、無言で私をきゅ、と抱きしめ返してきた。
「こんなこと、今言うのは酷だってわかってるわ。準備はいくらでもしていいから、ここをそういう場所だと思っていい。休んでいいわ、回復するまでいくらでも。でも…ここの外でみつけなさい。きっと、みつかるから」
「…深咲さんの意地悪」
「なんでよ、すごい優しいじゃないの」
「深咲さんが良い。深咲さんじゃなきゃやだ」
「私だって選ぶ権利があるでしょ、あんたみたいなの無理よ。面倒くさいし、重くて無理。責任持てない」
「……背負わせるつもりなんてないよ。僕は、ただあなたの横にいられればそれでいいもん。なにかしてもらいたいわけじゃないの」
そう言って新はにっこりと微笑むと、私にひとつキスを落とした。
なにかしてほしいわけじゃない、か。
でもだったら、なんで私が良いなどと言うんだろう。
…純粋な恋心っていつ失われていったのかしら。
どうしたってメリットとか、そういうのを考えてしまう。
でも、そうだなあ。
私も新になにかしてほしいとか、そういう感情はないけど。
でも、恋人にそれを求めないのはおかしな話じゃないの?
気付けば、私は抵抗するでもなくぼけっと考え込んでしまっていて新はそれをどう解釈したのか、気が付けばもう一度私にキスを施していて、それが随分と濃厚なものだった。
ぼけっとしてたのだから、もちろん唇を引き結んでいたわけではない。
であるからして、彼の舌が侵入してくるのはあまりにも容易だった。
ぬるりとしたものが口内に入って初めて我に返るなんて、いくらなんでも鈍い。
新と唇を重ねるのに慣れ切ってしまった証拠だろう。
「ふっ…んん、」
前されたとき思ったけれど、この男はやたらキスがうまい。
22歳よね。
……まあ、この容姿で女性経験が少ないって言っても信じられないけど。
数をこなしたからといってうまくなるわけでもないんだし、絶対に色々と女を悦ばせる才能があると思う。
ってそうじゃない、そうじゃないのよ。
これじゃあ流されてるみたいじゃないの!
抵抗しようと手を振り上げれば、新の腕が急に服の中へと入ってきた。
Tシャツ一枚しか着ていないのだから、大事な部分への到達は早い。
焦らすでもなんでもなく、新の右手が下着の中の突起をきゅ、と摘み上げた。
「あんっ!」
振り上げていた手がその行為によって停止してしまい、私の身体はびくりとのけ反った。
って、声をあげてる場合じゃない!
「や、ちょ、ああ!」
やめろ!と声を張り上げようとするけれど、新の手がまるでそれを阻止するかのように素早く快感を呼び起こす。
Tシャツも下着も胸の上までめくられて、いつもごはんを食べている場所でなぜ私は。
弟のようだと称した男の前で朝からこんなものを披露してるんだろうか。
Bカップというのがまたなんともむなしい。
ていうか、微妙なんだよな、私、大きさが。Cにいきそうでいかないという…
ってだからそうではなくて。
頭の中はかなり余計な事を色々と考えているのに、声を発しようとすると出てくるのは淫らな喘ぎだけ。
なぜ。
気持ちいいとか思ってしまう自分が憎い。
しょうがないじゃない、おとなだもの。失うもんなんてありゃしないわ。
付き合ってる男がいるとか、バージンだとか、そうだったらまた違う嫌悪感とかあるんでしょうけど。
だって新は綺麗な男の子だし、私に付き合ってるひともいないし、守りたいほど大切なものもないし。
そうなってしまうとどうしたって追ってしまう快楽。
まずい、まずい、まずい!
激しく揉みしだかれて、ふたつの丘は形をかなり歪ませている。
視界にはいったその頂が、恥ずかしいほど固くなっているのがわかる。
舌で這われて口に含まれれば、身体はどうしたって反応してしまう。
「あ、あ、ああ、もっ…」
「もっとしてほしい?ねえ、深咲さん」
妖艶に新がこちらに視線をやって微笑む。
あー、なんかもう、いいのかな。
いや、でもな。
ここを踏ん張らないと色々とまずい気がする…せめて否定の言葉を出せれば。それで成立する、はず。
「やめ…ああっ!」
タイミングを見計らって新がそれを施すから私の声はだめになる。
だああ、腹立つ!なんでこいつはこんなにうまいんだ。
ついに新の右手が私のスウェットズボンごしにそろり、と大事な場所を撫でてきた。
それに黄色だった信号が警報付きで赤くなる。
頭の中に鳴り響いたそれに、本能が動いた。
私は全力でもって、頭を起こした。
簡単に言ってしまうと、
頭突きだ。
『ごん!!』
思い切り鈍い音が茶の間に響き渡り、
あまりの痛さに新が顔を顰めて動きを止めれば私は間抜けだと思いつつも素早く横にごろごろと転がった。
下着とTシャツをぱぱぱっと直して寝そべった状態から起き上がる。
「いいったぁ…深咲さん、石頭…!」
「新、約束違反よ!…わかってるわね?」
仁王立ちして、私は腰にあてていた両手のひとつをあげて玄関方向を指し示した。
それに気が付いた新が真っ青になる。
「み、深咲さん!待ってよ、だって抵抗しなかったじゃない!」
「あんたねえ、私だってある程度の年齢いった女なのよ!?あんなことされてなにも感じないわけないじゃないの!」
「つまり気持ちよかったてことだよねえ?」
私の言葉に新がいやらしいニヤニヤ笑いをするので、私はそれに思い切り顔を顰めれば般若よろしく新を睨みつける。
「だからなに?気持ち良いからって誰でも彼でも寝たりしたら単なる淫乱でしょうが!動物でもあるまいし!!私達はね、人間なのよ。本能のままに生きるんじゃなく理性でものを考える生き物なの!」
「たまには本能のままになる事もあるよ、あの夜みたいに」
その返しに、私は額に手を当ててため息を吐いた。
ああそうさ!まったくもってそのとおりさ!!
「人生においてそういう事もあるものよ。大人だもの、過ちのひとつやふたつあるものだわ」
「なんか言ってること、色々と矛盾してない?」
確かに。
ここで出て行けと言うのもまあ、私だってすっきりとはしない。
けれどもこれまでのようにもうするんじゃない、と言って済ませるのもちょっとどうかと思うし。
少し悩んで、私はすとん、とその場に腰をおろした。
「…座んなさい」
言葉と、あと人差し指でくいくい、と床を指し示せば
新は無言でそれに従った。…正座じゃなくてもいいんだけど。
「新。ここでちょっと色々と確認しておきましょう。お互いの距離感を保つ事は、同居において重要なことだわ」
「…距離感?」
「そうよ。はっきりと言うわ。私はね、あなたをまったくもって信用していないの」
「深咲さん…」
私の放った言葉に、傷付いたかのように新の瞳が見開かれ、揺れる。
はっきりと今まで口にはしなかった。
けれども、たびたびこういうことが起こる以上は言わなければいけない。
「あなたの目的がもしもお金とか、そういうものであったとしたら、私はそれをとられてしまったとしても、まあいいかと思っているの。私にとって、私はそれほど重要なものではないわ。もしも新が私を傷付ける存在だったとしても、まあいいかと思ったからこそ、あなたをここに置いているの」
「そんなことしないよ!」
叫んだ新に、私は穏やかな笑みを浮かべる。
「私に隠している事があるわね?」
「!」
「事情があるのはわかっているし問いただすつもりもないわ。けれども、なにか重大な事を隠していてるんでしょう?身分を偽っているのかもしれないし、なにかやろうとしているのかもしれない。でも私は、それを深く知るつもりはないわ」
「深咲さん…」
「私達は、お互いにある程度の距離が必要だわ。身体を重ねて、ただの男女になってしまえば、それはひどく曖昧なものになってしまう。すべてをさらけだせない状態でそうなった人間の絆はとても脆いものよ」
「…………」
「あなたにどういう事情があってもかまわない。ここに置いた以上、なにかに傷付いているあなたが健やかになるまでここを休憩場所として提供するつもりだったの」
そこで一旦言葉を切れば、私はふ、と息を吐き出した。
「あのね、新。あんたが手負いの猫である以上、ここは新にとって我が家で、私は家族なのよ。女じゃないの」
「恋人だって、家族みたいなものじゃないか」
「心のなかをみせられないのに?」
「!」
「セックスがしたいのなら、他にもいくらでもいるわよ。でもね、あんたが束の間でも安心できる場所は今んとこ、ここだけでしょ?」
私の言葉に、新はこくり、とうなずく。
その様子に私は苦笑してしまった。素直なんだけど、ね。
「そんな場所でただ身体を重ねてしまったら、ここもいつか新にとって、むなしいだけでしかない存在になるかもしれないわよ。いいの?」
「それは…!」
「私達がこういう距離を保っているからこそ、『今』は成立しているのよ。いい?それを間違えてはいけないわ、新」
「……深咲さん」
「ん?」
「僕が、もしも、すべて終えて、本当の事を話したら…あなたは僕を男としてみてくれるの?」
「それは…どう、かしらね?わかんないわよ」
「だったらやっぱりやだ。これからも努力はする!」
「別に、態度をよそよそしくしろとか言ってないわよ。ただ、お互いに気持ちが追いついてないのに、そういう行為はやめましょうってことよ。単純に言えばね」
「僕はこのまま、ここで生活してもいいかと思ってた」
新の言葉に、私は眉根を寄せた。
「逃げるのは、駄目よ。っていうか…やっぱりなんかしてるのね」
質問に答える気はあるのかないのか。
新はただ苦笑するだけだった。
「別に、それに迷ってるんならやめたっていいと思うわよ?ただなにかから逃げてきたっていうんならそれを片付けてらっしゃい。そのあとにまたここで暮らしたいっていうんなら改めて話くらいは訊いてもいいし、その先だってまあ考えなくもないわ」
「え。それは…僕を嫁にしてくれるという…」
「いや、なぜ嫁なのよ。あんた婿ってずっと言ってたでしょ」
「あ、ごめん。なんか気持ち的についつい」
「あくまでも、スタートだけどね。対象外から枠内に移動させるくらいはしないでもないわ」
その言葉に、新はしばらく眉を寄せて何事かを逡巡している。
一体彼の脳内ではどんな事がまわっているのだろうか。
私はそれを見守るように、じっと新をみつめていた。
「改めて確認なんだけど。深咲さんは今フリーなんだよね?」
「何度も言ってるわよ。じゃなきゃあなたをここに置くはずもないでしょ」
「口説かれている人間とかは?将来的に恋人になりそうな男とか」
「いないってば。そういうのとんと縁がないのよ。言ったじゃないの」
「……じゃあお願い。僕がそういう立場にたてるまで、誰にも陥落しないで」
「…は?」
「だからあ、恋人を作らないでって言ってるの!僕がスタートラインに立ってからは行動を制限しないから。だって勝負する前から諦めなきゃいけないなんてそんなのないでしょ」
「…はあ」
あまりにも真剣な新の表情に、私はなんだか間抜けな返事をしてしまう。
それが気に入らなかったのだろう。
新はますます眉間に皺を寄せれば、私との距離を詰めた。
「それを約束してくれるなら、僕はあなたにそれまで手を出さない。どうなの?してくれるの、くれないの?」
「ちょ、わ、わかったわよ。わかったから!ていうか心配しなくともないって言ってるじゃないの!」
「わかんないじゃないか。このあとモテ期がくるかもしれない」
「馬鹿なことを言うんじゃないわよ。まったく…。とにかく、約束よ。挨拶程度のキスとハグ。それ以上は不可。いいわね」
「えー!ディープキスはアリだと思うんですけど!」
はいはい!と手をあげて発言する新に私は脱力する。
…なんだその、バナナはおやつに入るんですか的なノリは。
おやつ代は五百円まで…って違う。
「……あんたそっからいつも暴走するじゃない。却下よ」
「えー!!でもでも、深咲さんだって嫌じゃないでしょー!?」
いや、だから。そういう問題じゃないっつーの。
この子、さっきまでの話全部訊いてたのかしら。
なんとか説得を試みても新は嫌だを連発し、分からせるまでかなりの時間を要した。
仕事の日だというのに、朝からこんなに疲れて大丈夫なのか?
にしたって、なんでそんなにしたいのよ、キス。
本当に、そういう欲求は外で発散してくれなきゃ困るわ。
そう言うと、新はまた深咲さんにしたいのだと言うんだから。
なんだって私かなあ。好きだからか。
なんなの、手が早いくせに純情少年なの、あいつは。
…ああ、久々に頭が痛いわ。

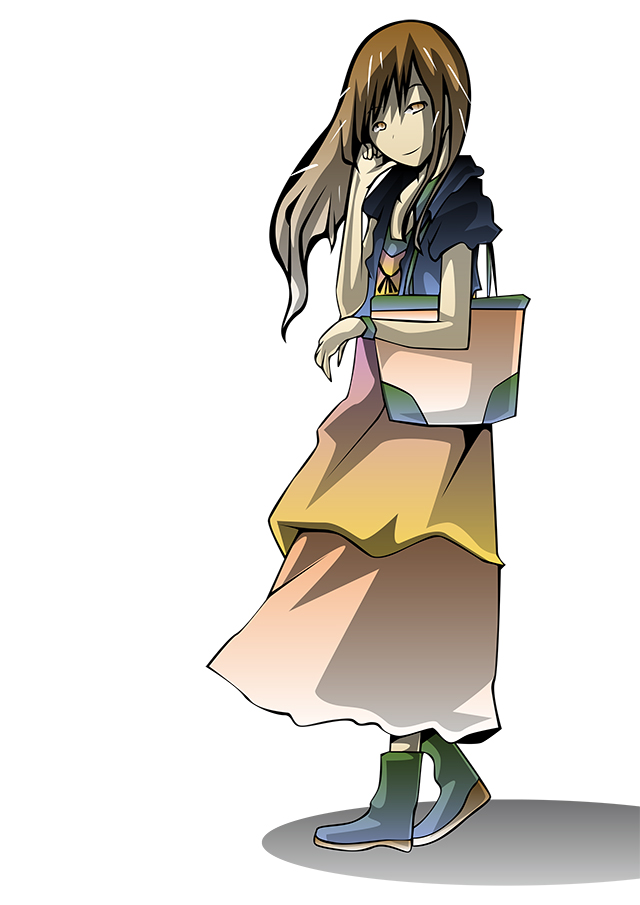

コメント