
「人間は、正直でなければならない、と最近つくづく感じます。おろかな感想ですが、きのうも道を歩きながら、つくづくそれを感じました。ごまかそうとするから、生活がむずかしく、ややこしくなるのです。正直に言い、正直に進んで行くと、生活は実に簡単になります。失敗という事が無いのです。失敗というのは、ごまかそうとして、ごまかし切れなかった場合の事を言うのです。それから、無慾ということも大事ですね。慾張ると、どうしても、ちょっと、ごまかしてみたくなりますし、ごまかそうとすると、いろいろ、ややこしくなって、遂に馬脚をあらわして、つまらない思いをするようになります。わかり切った感想ですが、でも、これだけの事を体得するのに、三十四年かかりました。」
太宰治「一問一答」
コンコン
『歴史研究部』の札が下がった扉が軽く叩かれる。
「どーぞー」
本棚の整理中だった遥歌が返事をする。引き戸が開いた向こうの影に遥歌は目を見開いた。
「どうしたの?本恐怖症の安がここに来るなんて」
「……本恐怖症って…」
もうすぐ夕暮れが訪れる時間。
「だってそうじゃない?補習は終わったの?」
「何とか」
学年末テストは終わり、部活動のない生徒は午前中に帰っていったが、安だけは引き続き授業をさせられていた。
「で、何の用?」
抱えていた本を机に置き、安に尋ねる。
「あ、そうそう、ハルに頼みたいことがあったんだ」
「?」
安は鞄の中をゴソゴソと探る。
「ハルさ、最近忙しい?」
「忙しい」
「……んじゃ、いいや」
「そこで、あきらめる?フツー」
「だって忙しいんでしょ?」
「何よ?」
やれやれ、と言った風に目を細める遥歌。安は鞄の中からあるものを取り出した。
「テスト終わったら頼もうと思ってたんだけどさ、これ訳せない?」
「訳?」
差し出されたのは一冊の古い作りの本だった。しかし、それほど傷んでいないのを見る限りでは本そのものはさほど古くないのだろう。分厚い紐綴じに固い表紙。淡い緑の外装を遥歌はまじまじと観察していた。
「古事記…って書いてるけど?」
「そうなの?」
行書で書かれたタイトルは安にとっては三文字の漢字だということがかろうじて分かるという程度だった。
「訳すも何も古事記ならあたし専門だからほとんど覚えてるし分かりやすい解説書やマンガも出てるわよ。どういう風の吹き回し?」
「うん…俺もよく分からないんだけど、父さんから俺にって」
安は例の郵便の件を簡単に話す。
「万夫さんが?聖書とかを遺言替わりに遺す人は聞いたことがあるけどねぇ…」
言いながら遥歌は本をパラパラとめくる。
「『臣安万呂……』ほら、やっぱり。これ古事記の序文よ」
遥歌は指でその内容をたどる。
「あ、中身もそーなんだ」
「うん……あ、違う」
「へ?」
「同じだけなの序文だけだわ。本文は全然違う」
「そうなの?」
「うん、だってホラ……って言っても分かんないか」
慣れた内容でないことが分かると途端に遥歌の目が輝き出した。爛々とした瞳でページを流す。
「あれ……何これ?」
指が不意に止まった。安も本を覗き込む。
「白紙……?」
目を疑った。それは中盤にさしかかった辺りから全く何も書かれていないのだ。途切れているのか、終わっているのか、その内容が分からないため、推し量ることすら出来ないが。
「変なの……前のページまでは普通なのに後半は真っ白」
遥歌も訝しげにその本を調べる。
「そもそも古事記なら一冊ってのも変よね…」
「何で?」
「古事記ってのは簡単にいうと神話の世界から史実まで書かれた歴史書でね。元々、三冊の本なのよ。上巻・中巻・下巻、とセット。原書の写しだったら厚さから見て、これを最後まで書いてちょうど上巻一冊くらいだと思うんだけど…。序文があるってことは、これが上巻なんだろうし」
「三冊ねぇ…」
「あんた、コレ本当に万夫さんからもらったの?」
「う…うん…多分」
「ちょっと預かっていい?万夫さんが遺したならただの不良品じゃないだろうから訳してみるわ。本文の内容も知りたいし」
「もちろん。それを頼もうと思ってたんだし」
「りょーかい。ちょっと時間かかるかもだけど、いいわよね」
嬉々とその本を鞄にしまう。
「でも万夫さん、安が古典まるでダメって知らなかったのかなぁ…。こんな本渡しても、あたしほどの古典好きってそうそういるもんじゃないし、訳せなかったらどうするんだろ」
「だよねぇ」
「あ、そうだ!話変わるんだけど、あんたテスト休み中バイトしない?」
本を鞄にしまうと、遥歌はコロッと話題を変えた。
「バイトって…何の?」
「書類整理とかデータ入力とか…あんたパソコン好きでしょ」
「好きって言っても動画見たりゲームする程度…」
「充分よ。少なくともあたしよりは詳しいんだから。じゃぁこれ、旗右先輩の部屋の住所」
「旗右先輩…?」
安の言葉に顔を上げる。
「そっか、知らないわよね。あの人、一人暮らしよ」
「一人……って、ずっと?」
「うん、理由はあたしも聞いてないけど、亡くなられたんじゃない?コンピュータのプログラムのバイトして生活してるみたいよ、ずっと」
「プログラム?」
「何か、すっごく腕もいいらしくてね、頭もいいし。あの人大学行かなかったじゃない?でもいろんな工学部とか……あと有名なIT企業とかからかなり熱心な勧誘されてたらしいわよ」
安は言葉を失う。住む世界が違うとは思っていたが…。
「ま、何でか知らないけど、それを全部断って今はそのプログラムのバイトで暮らしてるわけ」
「よくやるなぁ……」
遥歌は軽く笑う。
「でも学校の外では結構知り合いいるみたいだしね」
「いるの?」
「あの人の専門って物理でしょ?なのにダメモトで経済とか宮内庁関係の資料頼んだことが何度かあったんだけど、確実に持って来てるのよねぇ。あれは何か人脈があるとしか思えないのよ」
小さく首をひねって一息つく。
「あの人はかなり重度の人間嫌いで人付き合いなんて言葉まるで知らないし、そのクセやたらめったら偉そうなんだけど……」
遥歌は顔を上げ、安の目を見る。
「悪い人じゃないわ、絶対に」
絶対に。
「…というわけで…」
ガチャリ、チャッ、ガシャン
安の顔を見た途端、栄は二重の鍵とご丁寧にチェーンまでかけられた。
「ハルに聞いてなかったんですか?俺が来るってこと」
「自分より使えるのが来るとしか聞いてない。騙された」
古いモルタルアパートの薄い扉越しに言い放たれる。
「情報処理の成績はハルより上ですよ」
事実だった。万夫と暮らしていたとき、時間つぶしにネットやゲームばかりしていたからだ。
「それでも使えない奴には変わりない」
取りつくシマもない栄に安は珍しくムカッ腹がたった。
「使えるかどうかは、使ってから言ってください」
しばらくの沈黙の後、きしんだ音をたて扉が開いた。
「使えないとは思うがな」
通されたのは六畳ほどの古い畳張りのワンルームアパートだった。傷んだ壁紙にきしむ床。見渡すと所狭しと七台のパソコンが置かれているだけで、他の生活必需品は最低限。
「先輩って一人暮らしなんですよね?」
「この書類を六時までに入力しろ」
(会話が成立しない……)
仕方なく安は紙の束を受け取り、指されたパソコンの前に座る。そこで初めて紙を見て、その細かさに目を丸くした。
「これを……六時までに?」
「無理ならやめてもいい」
「や、やりますよ!」
大見栄きってみたものの
そんなうまく行くわけなくて
「無理だな」
一時間を過ぎた頃に栄がのぞきこんできて呟いた。
「え、で、でも……!」
栄はコートとカバンを差し出した。
「帰れ、人がいるだけ邪魔だ」
押し出すように玄関から追い出す。
「使えない奴はいらない」
安はアパートの前に止めていた自転車のスタンドを怒りのままに蹴り上げた
(何様のつもりだよ、まったく)ペダルに足をかけ、人の間をすり抜ける。鋪道を数分走ったあたりで安はブレーキをかけた。
「あれ……」
車道を挟んだ向こう側の親子連れのようなの人影に気付く。
あちらも自分に気付いたようで片方が大きく手を振った。
「やっすしクーン!どーしたのー?」
周りを全くはばからない高い声に安は慌てて車道を渡る。
「あれー?家この近くだっけ?」
黒い制服姿に長い金髪。
そして安の目に留まったのは、砂城の足にしがみつき後ろに隠れていた、自分の膝ほどの背しかない少女。ようやく歩き出した、と言ったくらいだろう。柔らかい毛をふたつに三つ編みにして、飾り付きのゴムでくくっている。
「あ、このコ紅音(あかね)。砂城の妹。砂城に似て可愛いでしょ?」
「妹?……ずいぶん歳離れてるんだね。いくつ?」
安が笑って頭を撫でようとするより早く目を伏せ砂城の後ろにまた隠れる。
「三歳になったとこ。ちょっと人見知りだけど気にしないで」
「は…はぁ……。それで砂城ちゃんは何でこんなところに?」
「栄クンの家もこの近くなのよ。それでちょっと用があって」
「でも旗右先輩、機嫌悪いかも」
ことのあらましを話すと、砂城は笑って安の背中をたたいた。
「栄クンはいっつもそんなものよ。明日また行ってみて!」
「う……うん」
「安、お帰りー。早かったんやな」
「西夜、パソコン貸して」
「え?う、うん。ウチの部屋にあるのやったら好きに使って…」
言うより先に、安はドタドタと西夜の部屋に向かった。そして帰り道に買ったタイピングソフトのCD—Rや本を取り出す。
(また栄さんの口の悪さが出てしもたんやなぁ)
夜中まで灯りのついた部屋を見て西夜は襖をそっと開いた。
「あ!ごめん!もう寝るよね!終わるから」
「ええよ、今日は客間で寝るから」
「ご、ごめん、ありがと」
一瞬考えた後、西夜は困ったように笑った。
「栄さんも東子と同じかも知れない」
「え?」
「生まれ持った能力のせいで生まれた時から苦しめられてきとった」
西夜は軽く手を伸ばすと東子の膝で眠っていた猫が目を開く。
「僕達の能力はそれぞれ全く違う。ただね、それが有益なもんとは限らない」
猫は西夜の足下に飛んで来た。
「むしろ、それが本人を苦しめることの方が多いんや」
安は首を傾げた。西夜は顔を上げ、笑う。
「栄さんとちゃんと話してみれば分かるわ」
「ウチはな、ひょっとしたら安みたいな人やったら打開策を見出せるんやないかと思ったんや」
西夜は眼下に広がる街を見つめながら聞こえない言葉を東子に呟いた。
「ウチらの呪われた力すらも救える方法がどこかにあるんやないかて」
その細い肩を軽く抱き締める。
「単にそう思いたいだけなのかもしれへんけど」
その手を東子はぎゅっと握りしめた。風が暖かみを帯びて来た。
「来るなと言ったはずだ」
「もう一日!もう一回手伝わせてください!」
安は栄のアパートの玄関で大きく頭を下げた。
「…………私の能力を聞いたか?」
不意の質問に安は首を横に振る。それを見て、栄は仕方ない、という風に頭をかいた。部屋に一つしかない窓を開け、そして右手だけ革手袋を外す。
「あ、普通だ」
安は思わず声を漏らす。
「?」
「先輩、夏でもそれしてたでしょ?しかも長袖で。結構噂になってたんですよ、大怪我の痕があるとか、義手だとか」
「………まあいい」
栄はしばらく何かを考えていたが、突然辺りを時折行き交う春先の揚羽蝶を一匹、手袋をしたままの左手で素早くつかんだ。
そして安に見えるようにしながら右手に持ち替える。
まるで手品でも見せるかのように。
安は目を見張った。それは本当に手品のような、しかし確かに何の仕掛けもないものだった。
蝶の羽根が燃え出したのだ。つかむ栄の指先の周りからじわじわと。火はすぐにその根元まで届く。
小さな蝶はもがく間もなく、灰になり地面に落ちた。
一瞬の出来事の唯一の証拠である指先の燃えかすを払い落とすとまた手袋を着けた。
「これが私の能力だ」
「これ……って……」
安の顔から血の気がひく。
「自分の皮膚に触れたあらゆる生物を無条件で焼き殺す能力」
簡潔な、残酷なまでに簡潔な答え。
『むしろ、それが本人を苦しめることの方が多いんだよ』
「私が意識しようとしまいと関係ない。触れた時点で相手は必ず炎に包まれて死ぬ」
悲しむでも憂れうでもない。事実のみをただ語る無機質な声。
「私達の持つ能力とは、貴様が思うほど楽しいものではない。これが最後の忠告だ。手を引け」
目の前の事実しか映さない瞳が安の姿をはっきりと映し出す。全く動かない険しい表情。安は俯いて軽く笑った。
「……できませんよ」
栄の目が眼鏡の奥で訝しげに細められる。首を傾げて少し困ったように笑う笑顔。
「やっと手が届きそうなんです。父さんが俺を捨てた理由に」
安は薄汚れた椅子にストンと腰を下ろす。
「父さんが俺を恐れた理由に」
栄は一瞬目を疑った。そこにあったのは先ほどまでの安からは思いも寄らない狂気にすら似たほどの決意を帯びた瞳。
「あの日から俺は人に嫌われることが何より怖くなった。父さんが何故、俺をあれほどに恐れていたのかをずっと知りたかった。その理由にやっと近付けそうなんです」
心の底で叫ぶような声。
「確かに俺にできることがあるのなら何かしたい。でも、それ以上に自分のことを知りたい」
「言っておくが、私はいまだに知ってよかったと思えるような真実を見たことがない」
「分かってます。でも知りたいんです。父さんが何を考えていたのか。俺が何者なのか。…やっぱり、知りたくなるものでしょう?」
言って笑ったその表情はいつも通りの安のものだった。
「そんなことのために死ぬつもりか」
「死ぬつもりはないですよ。俺を死なせないって言ってくれた西夜の言葉を信じてるだけです」
「話にならんな」
栄はもう一度、革手袋を取り素手を安の顔の前数センチにまで近付ける。
安は目を見開く。
「私がこの手をほんの少し動かすだけで貴様はすぐに死ぬ」
大きな白い手に遮られた視界。
「貴様が相手にするのはこんな能力を持った連中だ。水吹の兄にどれほどのことができる?私達に関わり続ける限り、そんな奴らに命を狙われると言うことが分かっているのか?」
体が小刻みに震える。さっきの蝶が灰になる映像が頭の中でフラッシュパックする。
(殺される……?)
体中から体温が引く。その時、安の目に、掌越しの栄の目が映った。ほんの少し、いつもよりほんの少しだけ細められた黒い瞳。
『太榎万夫の二の舞いにはなりたくないだろう?』ふいに押し戻された言葉。
すぅっと頭の中がクリアになる。この人は何故、俺を止めようとしている?
『放せ!』あの時、何故俺の手を振り払った?
かなり分かりにくい表現ではあったが、この人は俺を助けようとしていただけじゃないか。砂城や西夜の意見に逆行してでも。
『悪い人じゃないわ、絶対に』ああ、大丈夫だ。この人は俺を殺したりしない。
「………でも」
向けられた腕を安の手がつかむ。眼前にかざされた手は、安のものと何も違わない。
薄いシャツ越しに感じたその感触に今度は栄が軽く肩を震わせる。何も違わない。シャツ越しに触れる体温は熱いわけでも冷たいわけでもない。普通の人間の温度だ。
指に力を込める。今度は払い除けられないように。手を放してしまわないように。
怖くないわけではなかった。でも手を振りほどかれて悲しいのは自分ではない。彼なのだから。
「少なくとも旗右先輩はそんなことしないでしょう」
確信、だった。安なりの。恐らく人と接触することを長い間拒絶して来たその手は、しかし確かに血が通っていて、温かかった。
「……何故、言い切れる?」
「砂城さんも、西夜も先輩を恐れていなかった。それに……」
言いかけて、一瞬口をつぐむ。
これは理由になるのだろうか。
でも
「それに何より、ハルが先輩のことを信じてる」
もしかすると、ただの言い訳なのかも知れない。でも、それで十分だ、と思った。ゆっくり手を放す。ゆっくり手が引き戻される。
「……好きにしろ」
諦めたような、しかし決して否定的ではない声。右手を手袋に収めながら、栄は硬い表情のまま呟いた。
「それって……」
「言っておくが、私は貴様の協力は要らないし、協力もしない。せいぜい砂城達に付き合ってやれ」
「あ……あの…ありがとうございます!」
「…仕事…するか」
「はい!」
安は部屋の中に通された。
「タイピング!練習したんです!おかげで徹夜しちゃいましたけど!」
翌日、講堂から別れを惜しむ歌が流れていた。早桜にもまだ少し早い季節。風も冷たいまま一向に春色を帯びようとしない。
「卒業式までサボりますかねぇ、先輩は」
校舎の壁に背を預け、佇む青年に声がかけられた。
「天川か……」
「ま、ネクタイすらして来てないのを見ると、最初っから出ない気でいるんでしょうけど」
ネクタイを外した制服に革手袋に長髪。校則ではないため普段は制服のネクタイまでしてくる人はそういないが、卒業式にまで規則通りに服を着ないのは彼くらいだろう。
右手に持っていた紙袋を持ち替えつつ遥歌は苦笑した。
「お前は?」
「あ、あたしは来客受付なんで、今はヒマなんですよ。生徒会も一年は雑用ばっかりですからね」
遥歌の言葉で会話が途切れる。栄の顔をのぞきこんだ。
「……もしかして、キゲン悪いですか?」
「別に……」
「あ、やっぱり悪い」
栄は答えなかった。
「わっかりやすいなぁ、先輩は」
「うるさい。それで、何の用だ?」
「ああ、そうそう」
遥歌は大きめの紙袋を差し出す。有名デパートのロゴが大きく印刷された青い袋を栄は訝しげに受け取った。
「何だ?」
「ご卒業おめでとうございます」
眉間に皺を寄せたまま、栄は袋の中を探る。目についたのは花束だった。鮮やかな白を称えるユリのシベリアが数本寄せられただけの花束。
「大体、三年生って部活の後輩とかに何かもらうんですけどね。先輩はそういう人いないでしょ。だから、あたしから。迷ったんですよ。似合う花選ぶの。先輩は現金の方がいいかも知れませんけどね」
遥歌は大きな瞳で満足げに笑う。
「これでも結構、感謝してるんですよ」
「何を?」
「分からなければいいですよ。とりあえず、それだけ持って帰って下さい。女の子からのプレゼントは大人しく受け取るのが礼儀ですよ」
遥歌は空を仰ぐ。
「またいつでも遊びにきて下さい。仕事用意して待ってますから」
「………つくづく暇な奴だ、お前も」
花を袋から出そうともせずに、少し俯いた。伸ばした黒髪が冬風に揺れる。
微かに動く口の端。
黒縁の眼鏡の奥の瞳を見て、遥歌は目を丸くした。
「……先輩…今、笑いませんでした?」
「?」
顔を上げた栄は不機嫌そうに眉をひそめていたが、遥歌は声を殺して笑い出した。
「うわぁ…最後の最後ですっごい、いいもの見たかも……、あたし」
口を覆って笑う遥歌に栄は頭を押さえる。
桜の季節はもうそこまで迫っていた。
「琉クンを?」
学生が行き交うファーストフード店の一席で砂城は軽く声を上げた。
「うん、安に会わせよかと思うとる」
西夜はジュースのストローを曲げながら砂城に告げた。
「無茶じゃない?安クンにとっても琉クンにとっても」
「分かっとる。でも今のままやと絶対にダメだから……。賭けてみたいんや。安に琉真(りゅうま)を救えるか」
「無理でしょうね。砂城としては安クンをあまり内々にまで巻き込んでほしくないわ」
「でも、どうせそのうち池条さん達にも会う時が来るやろ」
「……小手調べってワケか」
砂城はポテトを一本口に運ぶ。
「で、琉クンに会わせてもどうにもならなかったらどうするの?」
「その時はそれまでや。ウチの見込み違いやったってことで」
西夜の笑顔に砂城も口の端だけで微笑を返した。
卒業式の会場の出口で安は待っていた
「安?あんた今日休みでしょ?」
生徒会でも係でもない安がいることに眉をひそめる。
「あのさ、ハルに聞きたいことあったんだ」
「何?」
「古事記にさ、火の神様っている?」
遥歌が言葉を止める。
「どしたの?」
「………………………………………………あんた、熱ない?」
実に深刻な顔で安を伺う。
「ないってば」
「どうしたのよ、古典恐怖症がこの間から」
「いや、まぁ、いろいろあって…」
「いろいろ、ねぇ……」
大きくため息をついた。
「火神って火之迦具土神のこと?」
「ああ、何かそんな感じの名前」
「でもねぇ、別に伝説を載せているって言ってもほとんどの神様が通り名だけ出て来てる感じなのよ。火之迦具土神なんて有名な方なんだけど、それでも描写は数行だからね」
「数行?」
「そりゃそうよ。千年以上昔の話よ。今のマンガや小説とは体系からして違うもの」
「そっかぁ……」
「で、話戻すとね、火之迦具土神ってのが結構有名なのは伊邪那美を殺した神だからよ」
安は思わず振り返った。
遥歌はキョトンと目を丸くする。
「殺した……?」
「う…うん、殺したって言うか。伊邪那美ってのは神の母なんだけど、火の神を産んだ時にそのせいで燃えて死んだって…」
『触れた時点で相手は必ず炎に包まれて死ぬ』
栄の言葉が思い出される。
その能力の本当の残酷さを。
「太榎安のことはとりあえず様子を見てみることにしました」
栄の言葉にゆっくりと振り向く。長い黒髪が日に透ける。
「そうですか」
飾り窓の向こうの青空がその姿を引き立てる。
小夜子が花瓶を持って入って来る。特に何も言わずに部屋の脇にある木製の小さな棚の上にシベリアを生けた。
「珍しいですね。栄が花を持って来てくれるなんて」
「貰い物です。私の部屋にあっても似合いませんし、何より花瓶を置いたりして水がパソコンにかかると困りますから」
「そう言えば…」
彼女の言葉に青年は眼鏡の位置をなおす。
「西夜が昨日来まして、安さんを琉真に会わせてみるそうです」
「琉真に?」
小さく頷き微笑んだ。
「無謀…としか言えませんね」
「やっぱり栄もそう思いますか?砂城も同じことを言ってたんですよ」
口を手で軽く押さえ声も出さずに笑う。
「あなたはどう思われるのですか?」
栄は尋ねる。彼女は顔を上げた。
「『あなたは』どう思われるのですか?」
静かな日だった。
「伊邪那美様」
翌日、終業式も終わり、安が帰ろうとした時だった。体育館に続く渡り廊下にさしかかったところで見慣れた二人の影を見つける。
「イズミ、トネ、部活行ったんじゃなかったの?」
「ん?いや、今日は昼からだから先にメシ行こうかと思って」
「太榎さん、その後体調はどうですか」
「うん、あの時はごめん」
「何?お前ら」
智樹が口を挟む。
「一週間くらい前かなぁ、道ばたで行き倒れてたんですよ」
「はぁ?」
「いや……行き倒れては……」
笑顔で限り無く誇大された事実を告げる架織に智樹は首をかしげる。
「あ、ヤベ!購買もうすぐ開くじゃん!オレ、先行くな、都音」
「はい、僕も……あ、太榎さん」
「?」
「気をつけてくださいね。この春休みはよくないことが起こる気がしますので」
言うと、意味ありげに笑った。
「面白い人ですよね。太榎さんって」
体育館の前でパンを一口かじり、架織は言う。
「そうかぁ?変なやつではあるけどな」
智樹の言葉にケラケラと笑った。
「俺ジュース買ってくるわ」
言って立ち上がった背中を見送りながらも架織はまだ笑っていた。
「面白いですよ、まったく」
強い風が通り過ぎる。
「今はまだ泳がせておきますね。太榎安さん」
髪が静かに揺れる。
「あなたのことを必ず手に入れます。僕と姉さんのために」
駆け巡る喧噪の中、そのつぶやきを聞いた人はいなかった。
白い廊下を歩く。すれ違う人もなく、ただ長いだけの廊下。
突き当たりから三番目の部屋を手の甲で軽くノックする。返事はない。
が、引き戸は軽く開いた。
白い部屋。
窓辺にあるベッドに腰かけた少年が顔を上げた。
「久しぶりです。西夜」
少年はその青い瞳を前に向ける。
西夜は軽く手を上げた。
「調子はどない?琉真」
静かな日だった。ひどく残酷な力。ひどく残酷な運命。
この世界がその只中にあるとは思えないほど
それは静かな日の出来事だった。

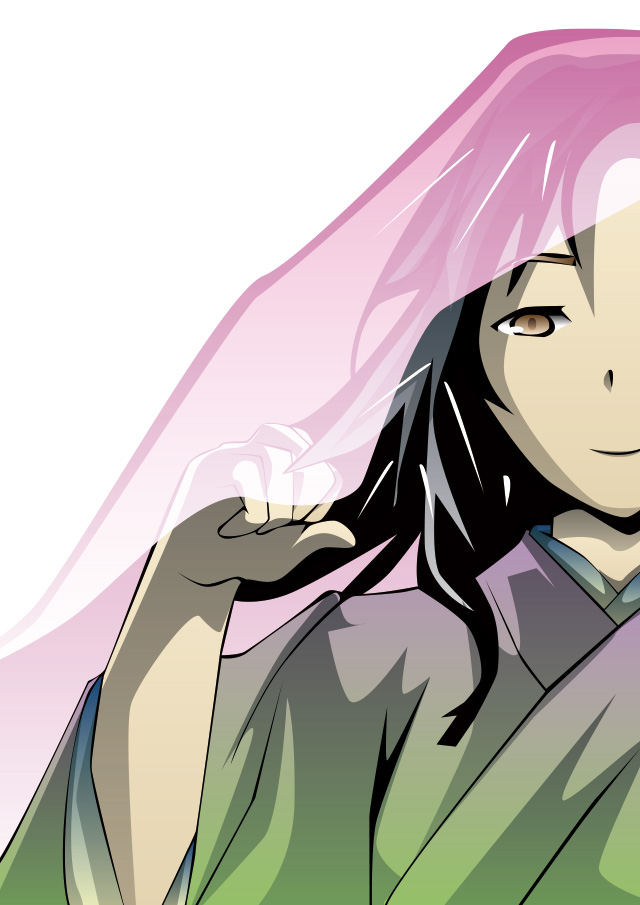

コメント